医療訴訟が招く医療崩壊
日本は世界で最も長い平均寿命を誇り、GDPに占める医療費の割合は先進諸国で最低の部類です。数字を見れば日本の医療制度は非常に成功していると言えます。しかし、そう思える日本人は次第に少なくなってきています。
医療費の負担は年々増加し、健康保険組合はどこも赤字で苦しんでいます。その一方で、医療現場では経営難を理由に病院が診療科目を減らたり、病院自体が閉鎖されることも珍しくありません。田舎では医者そのものがいなくなって最低限の医療さえ受けるのが難しくなってきています。都会でも救急車で緊急患者を搬送しようとしても救急病院の受け入れ先がなく、たらい回しは日常的です。産婦人科にいたっては救急でなくても出産を引き受ける病院がどんどん少なくなっています。
先進医療は今まで不治と思われていた病気の治療を次々に可能にしていますが、新しい治療法や薬は多くの場合保険の適用外で、有効と判っている治療を費用のために諦めなければならないことも増えています。その中で、医師の多くは40時間連続勤務などという非人間的な勤務体制で働いています。日本の世界的には安価な医療費は、医師の犠牲に支えられている面が多々あります。
このような問題の解決はどれも簡単ではありません。医者を増やすのも、救急病棟を増やすのも、先進医療を手の届くものにするのも、多額の費用が必要です。先進国の中で低い方とは言っても、今でも負担を軽いと思っている人は少ないでしょう。
しかし、医療費負担の増額とは必ずしも関係のない問題もあります。診療科目の違いによる医師の希望者の偏在です。医師が総数でも不足気味なのは確かなのでしょうが、診療科目によっては極端な不足があります。そしてその背景にあるのは多忙と医療訴訟のリスクです。
産婦人科は妊娠は病気とは看做されていないことからわかるように、何か起きると医師の責任が問われがちです。しかも分娩は昼夜を問わずという性質上、時間的にも制約の多い診療科目です。外科は手術という危険な作業を行います。外科医に対する訴訟は医師一人あたりでは内科医の3倍にもおよびます。
逆に、精神科などは医療過誤の訴訟リスクが低く、最近では人気科目です。耳鼻咽喉科や眼科も緊急手術や命にかかわる手術が少ないこともあり、希望者は増加傾向です。精神科や耳鼻咽喉科の医師になることが悪いわけではありませんが、緊急性を要し、命にかかわることの多い、脳外科医や心臓外科医の希望者が減少しているのは深刻な問題です。脳内出血などは手術までの僅かな時間の差が生死を分けるのです。
立場が変われば受け止め方が変わるのはよくあることですが、医療訴訟ほど、一般社会と医療関係者の見方が違うものも珍しいのではないでしょうか。医者以外の多くの人にとって、医療過誤に対する訴訟は、仲間意識でかばい合う医者の粗雑な医療行為から患者の権利を回復するためのある意味「正義の戦い」です。
その医療訴訟は年間千件ほどで、もはや珍しいものではありません。しかし、全体の医療行為の中ではごくごく例外的です。その例外的な医療訴訟が医師の職業的リスクを高め、極端な医師不足を起こす診療科目を作り出しているのです。
実は医療訴訟が本当に医療過誤と正しく対応しているかは疑問があります。1984年にハーヴァード大学が行った研究HARVARD MEDICAL PRACTICE STUDYでは、医療過誤による事故のほとんどは医療訴訟にならない半面、医療訴訟になったケースでは大部分が医学的には過誤とは言えないと結論付けられています。
司法の世界では、裁判官を始め法律の専門家が高度な医学的判断を行うのは事実上不可能です。医学的な判断を仰ぐために鑑定人が選ばれるのが普通ですが、鑑定人の意見が対立する時、裁判では鑑定人の肩書の権威が大きく影響します。一般的には開業医より、大学勤務、それも助教より教授の方が正しいことを言っていると判断されがちです。やむ得ないとは言え、これは正しい司法判断の方法とは思えません。
もちろん、医師の側に問題がないわけではありません。特権意識の下で、患者が医師を訴えるなどとんでもないと考え、医療訴訟に専門家として協力する医師を見つけるのは長い間極めて困難でした。現在でも、適切な専門家の支援を受けることは、訴える側に大きな負担になっています。訴訟に至るかはどうかは別として、明らかに怠慢、無知、不注意による「殺したも同然」と言えるような医療過誤もあります。しかし、そのような医師が極めて稀なのは間違いありません。大部分の医師は献身的に職業人として良質な医療を提供するように努力しています。
医療が製造業と比べて品質改善の余地が大きいのは確かでしょう。薬品の種類や分量を間違えるという基本的な医療過誤でも、ビンの形状などでエラーを防止する対策がとられるようになったのは比較的最近のことです。しかし、医療訴訟の多発が医療過誤の防止に役立っているかというと、そうとも言えません。医療にまつわるトラブルの多くは内密に示談処理をされることが多く、エラー情報の共有が十分に行われていないのです。この点では医療訴訟自身が情報共有の妨げになっているとさえ言えます。
医療過誤による事故の大部分が訴訟にならないということも考えれば、全体として見れば医療訴訟が医療過誤の被害を受けた患者の救済にもなっていないというのも事実です。現在の医療訴訟の多発は、医療の品質向上の効果も小さく、診療科目による医師の偏在という大きな問題を引き起こしています。
何より問題は若く、社会的にも経験の浅い医師たちが、訴訟という大きな不安の下で医療行為をしなければいけないということです。日本は医師が医療過誤により刑事罰で逮捕されてしまうことがあるという珍しい国です。訴訟や逮捕までの危険のある診療科目を希望しないことを利己主義と責めるのは酷というものでしょう。
医療訴訟のリスクへの影響は診療科目の選択だけではありません。手術だけでなく多くの治療に何枚もの同意書を取るのは普通のことですし、「可能性がないとは言えない」というものも含め全てのリスク説明をした挙句、「決定するのはあなたの自己責任」と突き放つのは、患者の側から見れば医師が無責任な態度取っているように感じらます。これでは医師と患者の相互の信頼を失わせる結果を招きかねません。
また、不十分な知識や経験による医療過誤であることに不寛容であると、飛行機の中での急病人の治療をためらう医師も出てきます。救急患者や難しそうな患者は受け入れないのが最善の策ということさえ起きています。
医療は人間を扱う性質上、常に人命の危険を伴います。だからこそ、医師は慎重な上にも慎重であるべきなのは言うまでもありません。しかし、医療行為に一般の業務上過失致死のような刑を、そのまま適用することは正当ではないでしょう。脳の手術などは1ミリの何分の一かの違いで患者を殺してしまうこともあり得ます。ミスが製品の不良になるだけの製造業とは違います。
また、工業製品との比較で言えば、人間は極めて個体差の大きなものです。薬に対する反応、臓器や神経の配置のばらつき。治療は本質的に「やってみなければ判らない」部分が多いのです。きちんと正しい治療を行っていれば、全ての誤りが業務上過失に問われることはないという考えもあるでしょう。しかし、ミスで逮捕されるかもしれないという恐怖は大変なものです。医療訴訟は例外的かもしれませんが、実際には手術中、治療中の死亡を完全に避けることはできません。
他の先進諸国の例を見ると、医療過誤に対し日本のような形で医師の責任を問う国は例外的です。スウェーデンのように患者の補償を行う患者保障法のような制度を持つところや、フランスのように第三者による仲裁手続き機関を作ることで、医師が訴訟により多大の精神的苦痛と負担を被らないように配慮が行われているところが多いのです。まして刑事罰での逮捕など、意図的な殺人でもない限り、極めて特別な事情がない限り認めるべきではないでしょう。
日本で具体的にどのような制度、手段が適当かは十分に検討が必要でしょう。しかし、肉親を失ったり、自分が大きな障害を負った、やり切れなさを医師が全て引き受けるような現状は正常とは思えません。反対する人は多いでしょう。しかし、医療過誤で医師個人を訴えること、特に刑事罰を与えることに制限を加えることは日本の医療の健全化のためには必要だということはもっと認識されるべきです。残念ですが、政府、厚労省は医療訴訟が医師に過大な負担を強いているという問題に大きな関心を持っているように思えません。恐らく、厚労省の最大関心事である医療費抑制と医療訴訟は直接関係ないと考えているからでしょう。しかし、医療費が高騰するより、お金を払っても治してくれる医者がいない方がよほど深刻なのではないでしょうか。
(本記事は「ビジネスのための雑学知ったかぶり」を加筆、修正したものです。)
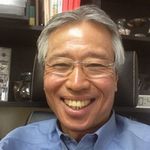
馬場 正博 (ばば まさひろ)
経営コンサルティング会社 代表取締役、医療法人ジェネラルマネージャー。某大手外資メーカーでシステム信頼性設計や、製品技術戦略の策定、未来予測などを行った後、IT開発会社でITおよびビジネスコンサルティングを行い、独立。







