「ピーターの法則」と「パーキンソンの法則」からみた企業弱体化の法則
最初にお断りしておきますが、このブログ記事は決して「うちの社長には先見性がない」とか「部長は決断力が全然ダメ」とかいつも言っている人達に同調するものではありません。上司は大抵部下より視野が広く、経験も豊かで有能です。それに上司や会社の悪口を言っている人達の多くは別に会社を辞めようと思っていないし、会社が潰れるとも思っていません。悪口はせいぜい酒の肴か仲間意識を高める道具に過ぎません。しかし、会社というものはバカとまでは言わないまでも、理論的には有能とは言えない人ばかりで構成される可能性があります。
ピーターの法則は消滅したのか?
今から50年近く前の1969年、アメリカの教育学者のローレンス・J・ピーターが「ピーターの法則」という本を出し、その中で「人は能力のある限り出世する。するとついに能力以上の地位まで昇りつめる。組織の階層は能力以上の地位まで出世した人で埋め尽くされる。組織の仕事はまだ能力以上の地位まで出世していない人によって、かろうじて遂行される」と述べました。この「ピーターの法則」は当時大きな話題となりました
ピーターが本を著した1960年から70年代にかけて日本は高度成長の真っ盛りで、企業の昇進の基本は終身雇用と年功序列でした。これはアメリカでもそうで、当時のアメリカの大企業のホワイトカラーは終身雇用が一般的でした。終身雇用が崩れ出したのは、アメリカでは日本との競争に製造業が負け始めた1980年代。日本ではバブル崩壊の後の1990年代になってからです。
終身雇用が一般的だったころは、アメリカでも同じ会社に勤務し続けている限り少しづつでも昇進を続けるのが普通で、降格されるようなことは滅多にありませんでした。そのような組織では確かに多くの階層が、もはやこれ以上出世できない「無能レベル」の管理者によって多く占められていたのは事実だったと思います。しかし、終身雇用が崩壊し、能力主義が徹底してくると、降格は当たり前、管理職の多くは転職組となってきます。現代では「ピーターの法則」がそのまま適用できる企業は少数派で、それが最近では「ピーターの法則」が忘れられてしまった理由でしょう。
しかし、外部から人材をスカウトしたり、降格人事を実行しても、ほとんどのポジションがそこが能力の限界の人たちに占められてしまうのは、理屈としては正しいように思えます。つまり、大部分の社員は「何とか無難にその仕事こなす」ことはできても、「すぐに出世してその地位を抜け出す」ような人は例外的なはずです。「ピーターの法則」が完全に消滅したわけではありません。
無能とは何か?
「ピーターの法則」は無能レベルの人で会社が埋め尽くされてしまうという話ですが、そもそも無能とは何でしょうか。アメリカのコーネル大学の二人の心理学者が、この問題に科学的に取り組みました。二人はユーモアのセンス、論理力、文法などいくつかのケースを取り上げ、それぞれについて初級者から上級者まで4段階に分けてテストを繰り返しました。その結果判明したのは、
- 初級者ほど自分の実力に対する評価誤差が大きく、かつ高く評価する傾向がある
- 初級者ほど他人の能力を評価するときの誤りが大きい
という二つの事実です。つまり、「無能」であるということは、単に何かを上手に出来ないだけでなく、「無能であっても自分は結構できると評価」し、かつ「他人の無能さ有能さは十分に認識できない」ということなのです。この結論を人事評価にまで広げてしまうのは異論もあるでしょう。人事評価は文法力のような単一の能力だけを評価するのではなく、協調性や目的達成への執念なども勘案されるからです。しかし、「あんなバカにとやかく言われたくないよ」と思うことは誰にでもあるはずです。
一般的には「上司は自分を高く評価してくれない!」というのは、そんな愚痴を言うこと自体が無能の証拠であるケースが多いのですが(無能に関する研究は上司にだけでなく部下にも当てはまります)、世の中には少なからず「自分の無能さに気づかないまま、誤った人事評価を繰り返す」上司が出現する可能性はあるわけです。このような上司は自分が無能な上に無能な人間を昇進させる危険が高く、無能は拡大再生産されることになります。いわゆる「類は友を呼ぶ」の無能人間版ということになります。しかも、無能な上司は自分自身を過大評価する傾向があるわけですから、「お前はわかっとらん」と喧嘩をしても、ただただ人間関係を悪くするだけの結果になってしまいます。
「ピーターの法則」と無能な上司は無能な部下を評価するという研究結果を合わせると、企業では無能な管理職がポストを占め、さらに無能な部下を昇進されるという悲劇的な状況が生まれることになります。企業が独占的で競争が乏しいと、この状況は悪化の一途をたどることになりがちです。大企業が突然坂道を転がるように業績を悪化させ、有効な手がまったく打てないような場合、その会社はいつの間にか無能者の集団になっているのかもしれません。
パーキンソンの法則
「ピーターの法則」は個人の資質を問題にしたものですが、組織が合目的的に機能しているかはもっと重要です。「ピーターの法則」の15年ほど前、英国の政治学者のシリル・ノースコート・パーキンソンは1955年にイギリスのエコノミスト誌で「仕事量は与えられた時間を使い切るまで膨張する」と「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」という二つの「パーキンソンの法則」を発表して、大きな話題を呼びました。パーキンソンは、この皮肉とユーモアに満ちた読み物で、イギリスの植民地省が第2次大戦後、イギリスが植民地を失うのに逆比例して職員数を増やし続けた現象をもとに、この法則を発見(?)したと書いています。しかし、「パーキンソンの法則」は官僚機構にだけ適用されるものではありません。とめどなく膨れ上がる間接部門はどこの会社でも悩みの種ですし、経費削減で「必要性の高いものに絞って」と言っても効果は乏しく、一律10%カットのような方法しかないのが普通です。
パーキンソンの法則の背景にあるのは、雇う側と雇われた側の利害が必ずしも一致しないという事実です。株主が取締役を雇い、取締役が経営者を雇い、さらに経営者が管理者を雇って会社の資源を有効に活用しようとしても、雇われた方は雇う側ではなく自分たちのために資源を使おうとする傾向があります。これは経済学でいう代理人問題あるいはエージェント問題という現象です。パーキンソンは国民という雇い主の意向に反して雇われている側の役人が予算を使いきってしまうことを指摘したわけですが、企業も取締役以下全ての人が雇われている以上「パーキンソンの法則」から逃れることはできません。
コースの定理
会社が無能者ばかりになってしまったり、たとえ能力があっても自分たちのことしか考えないような社員ばかりになるとすると、なぜ会社など作る必要があるのでしょうか。ロナルド・コースはそれは企業の中で行われる内部取引が他社と行われる外部取引より安いからだと説明しました。これは確かに一理あります。他社との取引は契約書を交わしたり時間がかかりがちですし、利害が衝突することもあります。コースは「取引には取引コストが必要で、そのために取引コストを節約する方向で組織が編成される」という「コースの定理」を提唱し、その業績でノーベル経済学賞を受賞しました。しかし、「コースの定理」は万能とはとても言えません。企業が巨大化すると内部取引の方が外部業者よりコストも時間がかかるようになるのは日常茶飯事です。それに取引コストが一見小さくとも本業と関係の薄い事業を抱える無駄もあります。アウトソースの普及は巨大化への反省です。
確かに、海底油田の探索、巨大ジェット旅客機の製造、長年の研究を要する新薬の開発、こういったことができるのは大企業しかありません。しかし、企業が成長し組織が肥大化するとそれによる弊害ばかり目立つようになるのも事実です。「うちの社長は先見の明がない」などと嘆いている暇に、大企業の鼻を明かすようなビジネス立ち上げを考えたらどうでしょうか。どうせ相手はバカばかりなのですから。
(本記事は「ビジネスのための雑学知ったかぶり」を加筆、修正したものです。)
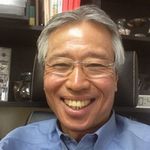
馬場 正博 (ばば まさひろ)
経営コンサルティング会社 代表取締役、医療法人ジェネラルマネージャー。某大手外資メーカーでシステム信頼性設計や、製品技術戦略の策定、未来予測などを行った後、IT開発会社でITおよびビジネスコンサルティングを行い、独立。







