利己的遺伝子と囚人のジレンマ
池の中でメダカの群れを見ると驚くほど整然と統制のとれた泳ぎ方をしています。何十匹、何百匹のメダカがまとまって泳ぎ、時々一斉に方向を変えるのを見ると、群れを指導するよほど優れたリーダーがいるのではないかと思えてきます。しかし、実際はそうではありません。メダカの群れは各々一匹一匹が自分の生存の利益を追求する結果として、あのように群れとしてまとまった動きをするのです。
生物学者であるジョージ・ウィリアムズは「生物はなぜ進化するのか」という著書の中で、魚の群れについて分析をしています。メダカのような小さな魚はいつも、より大きな魚や水鳥のような捕食者の脅威にさらされていますが、捕食者に襲われたとき、一匹だけでいるより群れでいれば、運の悪い一匹は捕らえられても他の魚は助かる可能性は高くなります。10匹の群れなら食べられてしまう確率は10%ですが、100匹では1%です。ですから、群れが大きいことは群れの構成員のメダカに有利に働きます。
群れる事が万事合理的な判断か?
ところが、群れがあまり大きくなりすぎると好ましくない事態になります。群れが大きくなればなるほど、群れの構成員が食物を分け合うことが難しくなり、競争が群れの中で始まります。また、群れが大きくなると捕食者の目にとまる確率も高くなるわけですから、かえって危険が増してしまうことも考えられます。
今、群れにいるメダカの数に、捕食者の注意を引いたり食物をそれほど争わなくても良い程度に小さく、かつ捕食者に襲われたとき助かる可能性が十分に大きい最適規模があったとして、それが100匹だと仮定しましょう。群れの大きさが200匹になったとき、群れが取るべき最適な戦略は群れを二つに分割することです。ところが個々のメダカにとっては群れを抜け出して一匹になることは自分だけが危険な目に会うことですから、そんなことはしません。メダカの中に指導者がいて、「このままではいけない群れを分割しよう」という決定を下せば良いのでしょうが、メダカの群れに指導者はいません。
結果として、メダカの群れは大きくなって規模の不利益が生じるようになっても分割されることはなく、何かのきっかけで群れの誰かが向きを変えると遅れないように一斉に向きを変えて整然とした回遊を続けることになります。実は指導者がいなくて、それぞれが自分勝手に行動していることがメダカが集団行動をとる原因だったというわけです。
メダカは囚人のジレンマを学べるか
集団の構成員が勝手なつまり利己的な行動を取ることで、集団としての利益も各構成員の利益も損なわれてしまうのは、ゲームの理論で有名な「囚人のジレンマ」とよばれているものです。「囚人のジレンマ」の設定では、二人の囚人が別々に尋問されています。互いに片方が、どのように尋問に答えるかはわかりません。どちらも黙秘を続ければ二人とも懲役3年、片方が黙秘して、一方が自白すれば、黙秘した方は懲役10年になるが自白した方は懲役1年ですむ、どちらも自白すると二人とも懲役5年、という状況でそれぞれの囚人の戦略を考えるものです。
この場合、両方にとって一番望ましい対応は双方が黙秘を続けることです。ところが、別々に尋問されている二人は相手が自分を裏切って先に自白してしまう疑惑から逃れられません。自分だけが黙秘を続けると懲役10年になってしまうので、どちらの囚人の戦略も速く自白してしまうことになってしまいます。自分の利益だけしか考えないことで結果として、自分自身の利益も最適化できなくなるというジレンマに陥ってしまうわけです。
しかし、メダカは尋問されている囚人のような知恵はありません。それなのにどうしてメダカは皆ゲーム理論の「囚人のジレンマ」と同じ解にたどり着いてしまうのでしょうか。それはメダカには「群れを離れない」という行動様式が進化の中で組み込まれたからに他なりません。そして、そのメダカの行動様式を決定づけているのはメダカの遺伝子です。ドーキンスは生物の行動を操って自分のコピーを増やそうとする遺伝子を「利己的な遺伝子」と呼んでいます。ドーキンスによると遺伝子にとって個々の個体は単なる遺伝子の乗り物に過ぎず、一見メダカの生存のための行動も「利己的な遺伝子」に奉仕するためのものだからです。
メダカ遺伝子の戦略
「利己的」というのは擬人化した言い方ですが、あたかも遺伝子が意志を持っているように言うとメダカの遺伝子は自分の(生殖行動の結果作られる)複製を残そうとします。遺伝子の乗り物であるメダカが食べられてしまっては複製を残すことはできませんから、まずメダカを生き残らせることがメダカの遺伝子の戦略になります。しかし、これではメダカ=遺伝子ということですから、遺伝子が利己的とは思えないかもしれません。
ここでジョージ・ウィリアムズはミツバチの例を持ち出します。ミツバチには雌である女王蜂と働き蜂がいますが、働き蜂には生殖能力はありません。したがって働き蜂は自分の遺伝子を残すことはできないように思えます。ところが遺伝子を残す手段は子供を作ることだけではありません。一つの蜂の巣の中の働き蜂は全てメスで同じ女王蜂から生まれますが、実は父親にあたる雄蜂は遺伝子を一組しか持っていません。つまり全ての働き蜂は同じ父方からは同じ遺伝子を受け継ぎます。女王蜂の方は人間と同じで遺伝子を二組持っていますが、結局姉妹になる働き蜂どうしは遺伝子の75%が一致することになります。ちなみに人間のような父方、母方ともに遺伝子を二組持っていると、遺伝子が自分と一致する割合は親も兄弟も子供も同じで50%です。
働き蜂は巣が外敵から襲われると猛烈に戦います。そして戦って針を相手に突き刺すと自分も死んでしまいます。しかし、その結果巣が守られるなら自分の遺伝子の75%分は守られることになります。遺伝子の視点で考えると、一見利他的に見える働き蜂の戦いも、実は遺伝子にとっては利己的な行動だということになります。
もちろん実際には、遺伝子に意志などはありません。利己的な遺伝子という表現は、遺伝子が自分のコピーを沢山残す確率を増やすために生物に特定の行動パターンをいわばプログラムすることに他なりません。しかし、「利己的」という性質は、感情や意志を持った人間と同じように利己的であるがゆえに「囚人のジレンマ」に遺伝子を陥らせてしまうのです。
会社のために自ら退職する社員はいない
人間は高度な知能があるので、メダカやミツバチのように単純に遺伝子によりプログラム化された行動様式はとりません。しかし、人間を「囚人のジレンマ」に縛りつけてしまう利己主義は、もとはと言えば利己的な遺伝子が自分のコピーを沢山残そうとした結果として人間に与えた属性です。人間の欲望の根本に遺伝子があることは間違いありません。
人間の文明はある意味利己的な遺伝子との戦いと言えるかもしれません。個人の勝手な(つまり利己的な)活動を罰し、全体への奉仕や協力を重んじるようになったのは遺伝子がそのように変化したからではありません。人間はメダカと違って最適なサイズを超えて大きくなった群れを二つに分割する知恵を文明によって身に着けるようになったのです。
とは言っても、最適なサイズを超えて大きくなった企業を分割するのは容易なことではありません。会社の風通しを良くし、より機動的に動けるようにするために進んで退職する人など滅多にいるものではありません。事業部制度や社内ベンチャーという形で分割する試みはありますが、一つの会社あるいはグループである限り社内調整や資源配分に大きな手間と努力を必要とするのは普通です。
個々の利己主義を集団の利益にどう一致させるかが「囚人のジレンマ」をどう解くかにかかっているという点では、人間もメダカもそして遺伝子も本質的な差はありません。「とかくメダカは群れたがる」と言いますが、群れてしまう理由はとても根深いのです。
(本記事は「ビジネスのための雑学知ったかぶり」を加筆、修正したものです。)
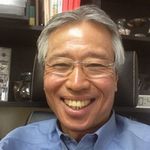
馬場 正博 (ばば まさひろ)
経営コンサルティング会社 代表取締役、医療法人ジェネラルマネージャー。某大手外資メーカーでシステム信頼性設計や、製品技術戦略の策定、未来予測などを行った後、IT開発会社でITおよびビジネスコンサルティングを行い、独立。







