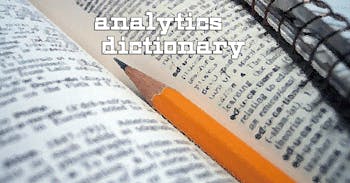目次
組織運営の鍵は「非公式コミュニケーション」
本日は、『職場の人間科学|ビッグデータで考える「理想の働き方」』(ベン・ウェイバー著)を読み解きます。
また、本書に関連するニュースとして、「中居さんにセンサー装着 がんこフードの科学接客」という日経情報ストラテジーの記事も昨日(6/27)公開されていますので、興味のある方はご一読をおすすめします。
本書の概要(ビッグデータは目的ではなく手段)
技術の進歩により、「人の行動」が分析できるようになった。その人がどこにいるのか、その人が誰と会っているのか、どういうコミュニケーションを取っているのか。しかも「会話の内容」に依らず、「コミュニケーションのシグナル」を分析するだけで「行動特性の把握」には十分であり、且つ、プライバシーに配慮できることも分かった。
つまり、センサー技術により、「どこに(敷地内のアンテナとの距離)」「誰と(相手のセンサーとの距離)」「どういう具合に(声量・声の高さ・強弱など)」会話しているのかということをリアルタイムで抜き出すことが可能となり、その結果、”人のどういう行動が業績に影響を与えるのか”を解析できるようになったのである。
本書では、組織において、コミュニケーションがどのように行われているのか、そして、それが企業としての効率や業績、労働者の満足度などに、どのように影響を与えるのかを解き明かし、組織の在り方(M&Aなどにも転用可能な組織論として)を考えていく。
データは「どう読むか」が重要
概要をご一読いただいてわかるとおり、本書において「ビッグデータ」という言葉で通常表現される事象・事例は、本質的なトピックではありません。
これは、原題を読んでも明らかです。
原題は「People Analytics | How social sensing technology will transform business and what it tells us about the future of work」ですので、センサーテクノロジーが働き方を変える、というのが主題になります。
本書において、データ(センサーデータ)はあくまでもインプットであり、また、どう取得し、どう分析するかという話も副次的なものにすぎません。もっとも重要なのは「そのデータから何を読み取るか」なのです。
ギックスでも、再三にわたり「データアーティスト」の重要性を述べていますが、本書も「データから人間の行動を理解する」という目的ありきで語られているわけですね。(関連記事:データアーティストとは何か)
センサーデータがピープルアナリティクスを変えた
本書の冒頭で”日本語版への序文”ということで、センサーデータについて語られます。(そして、おそらく、本書で唯一「ビッグデータ」という言葉が使われる場所だと思います)
日本人、そして人類全体が新しい世界の扉の前に立っている。その扉が現れた原因は(中略)データである。それも、ただのデータではなく、ビッグデータだ。そのビッグデータは、新しくて力強く、これまでに世界が見たことが無いものだといえよう。
そのデータは人間の行動を表すものであり、目には見えないけれど、実感することができる。このデータが測るのはカリスマ性や影響力、想像力など、これまでは主観的にしか把握されていなかったものだ。このまったく新しいデータは、まったく新しい技術、つまりセンサーから取得されている。
そして、このセンサーデータを「センサーバッジを装着させる」ことによって収集し、それを分析していくことで、様々な組織における「人の行動」を解き明かしていきます。具体的な事例や内容は、本書をお読みいただくとして、僕が興味を持ったポイントを幾つかご紹介させていただきます。
カッチリとした「組織図」の弊害
組織図には面白い特徴がある。ほとんどの組織は、コミュニケーションがすべて組織図の線に沿って行われているかのように運営されているのだ。この観点kら観れば、組織図上で直接の関係が無い相手とは、会話をする必要はないという事になる。
この点こそ、従来の経営理論の穴なのだ。
つまり、組織図によって、機能配置が明確に行われていればいる程、その組織図に基づいたコミュニケーションが定義されてしまう、ということになり、それが「非公式なコミュニケーション」を減らすことになる、というわけです。
凝集性と多様性
本書では、組織を「凝集性が高い組織」と「多様性が高い組織」という二つに大別します。
本書では、「凝集性」とは、人々同士が会話する集団-つまりネットワーク-のつながりの強さを指す。凝集性の高いネットワークとは、人々が互いにたくさん会話をする集団だ。ネットワークをクモの巣と考えてみてほしい。点を人間、線をコミュニケーションとすると、凝集性の高いネットワークは、糸がぐちゃぐちゃに絡み合ったクモの巣のような格好をしている。
本書で「多様性」という言葉を使う時には、たいてい人口統計的な意味での多様性ではなく、社会的なつながりという意味での多少性を指すものとする。つまり、同じ集団内の人とばかり話しているのか、それともネットワーク内のいろいろな人々と話しているのかだ。多様性の高いネットワークは星のような形をしていて、中心にいる人物から多方面に線が伸びている。
凝集性が高い例としては、バスケットボールチームの例が挙げられます。相互理解が進むことで、高速な非言語コミュニケーションが可能となり勝利に結びつくわけですね。しかし、凝集性が高い、ということにも弊害があります。
凝集性が高いといっても、あまりに行きすぎてしまうと、いろいろなデメリットも生じてくる。(中略)閉鎖的なネットワークの中にいると、新しい情報を発見するのは信じられないくらい難しくなる。また、他者に影響を与えるのも難しい。凝集性の高いネットワークは極めて内向きなので、さまざまな利害関係者と接触を取り、大きな変革をもたらすのは難しいわけだ。
一方、多様性の高いネットワークはその逆で、凝集性の高いネットワークが苦手とする物事が得意だ。古い習慣を捨て、見方を変えるのに適しているのだ。
そして、そのどちらが良いのか、については「バランスである」と著者は結論づけます。
安全地帯から抜け出すのも(田中注:多様性を求めるのも、の意)、凝集性の高いネットワークを築くのも、おおむね良いことだとすれば、どちらを選ぶべきか?多くの研究者は煩労するだろうが、「白か黒かではない」というのが答えだ。大半の時間を一緒に過ごす密な集団を築くと同時に、多様なネットワークにも属して、ときどき新しい情報を仕入れることもできるのだ。
どう、組織をつくるのか。あるいは、どんなポジションを目指すのか。
本書を読んで「ビッグデータすげぇ」あるいは「センサーデータやべぇ」となる人は限られていると思います。冒頭でも書いた通り「これらのデータから読み取った結果の”組織の在り方”」に対して、「自分はどう振る舞うべきか」を考えることになるのではないでしょうか。(研究者ではない、一般のビジネスマンなら、むしろ”そうあるべき”ではないかと思います)
さらにいえば、「組織設計」を業務において行う人は稀でしょうから、まずは「自分がどういう振る舞い方をするのか」を考えることになるでしょう。
そういう場合に、最初に考えるべき概念は「媒介中心性(betweenness centrality)」だと思います。
媒介中心性が高い=代替が効きにくい
非常にざっくりいうと、複数のネットワークを「つなぐ=媒介する」役目を担う人が「媒介中心性が高い」人です。そして、そういう人ほど、権力や影響力を持ちやすくなります。
一般的に中心性の高い人物ほど、大きな権力や影響力を持ち、他の人々よりもいち早く情報を得られるというのは容易にわかる。
結局のところ、組織における個人としての価値を最大化するには「媒介中心性」を高めるという事だと僕は思います。もちろん、組織全体の運営からすると、特定個人にたよってしまうのは危険なのですが、適性や相性の問題もありますので、致し方ないことだと思います。(本書では、それを打破するために、ウォーターサーバーの設置や、食堂の家具選定、デスクの配置などに拘ることを示唆しますが、即座に変えられる企業は少ないでしょう)
この個人としての「媒介中心性」を高めると、あなたは、会社にとって代替が効きにくい存在になります。「わからないことはアイツに訊け」もしくは「誰に訊けばいいかわからないときは、まずアイツに相談しろ」ということになります。
他社でも使えるスキルなのか?
一方、このスキルは鍛えれば鍛える程「転職しても(≒他部門に移動しても)使えるのか?」という疑問を生じさせるスキルでもあります。
が、敢えて断言しましょう。「大丈夫、どこに行っても使えます。」と。
基本的に(つまり、一部の例外を除いて)、組織と言うのは、組織図に沿って組み立てられています。ですので、硬直化したコミュニケーションが世の常です。そこに風穴を開ける、というのは簡単な事ではありません。ですから、どの企業でも求められている「能力」なのです。
もちろん、慣れるまでに時間がかかるでしょうし、入るポジションや、会社のフェーズ(拡大期なのか、低迷期なのかなど)によっても、振る舞い方は変わります。しかし、それでも「媒介中心性」を築くことはできます。要するに「今の会社の媒介中心性」は次の会社では使えませんが、現在の媒介中心性を築いた「媒介中心性の獲得スキル」が使えるわけです。
スキルとして説明しにくいのが現状
とはいえ、一つ問題があります。それは「スキル」としての説明が難しいのです。
転職市場において「何ができるの?」という問いは必ずでてきます。何を成し遂げたのか、それが、新しい職場でどう活きるのか、と。
その問いに、このスキルだけでは答えにくいのです。
ですので、現時点では、他のスキル・経験(例えば、プロジェクトマネージメントや、事業開発・事業立ち上げ経験など)を核とて応募しながら、面接では、自分が媒介中心性を築きやすい会社かどうか=自分の強みが活きる職場かどうかを見極めることが重要になります。
しかし、本書のように「データに裏打ちされた組織の新しい”あるべき型”」を提言してくる風潮がすすめば、「コミュニケーションプロフェッショナル」などのようなスキルセットが認知されてくるのではないかと思います。(もちろん、あと数年は必要でしょうが) そうすると、このスキルは非常に普遍的に役立つものになると僕は思います。
今後、各企業は、おそらく、本書で書かれたような「組織として、非公式コミュニケーションを活発化させる仕組み」をつくっていくことになると思います。しかし、「人はそんなに簡単に変わらない」と僕は思うのです。いくら組織図を変え、いくら休憩時間を調整し、食堂でのコミュニケーション活発化を推進しても、コミュニケーションの中心・核となる人は、固定されます。
その「核となる人材」になるためにどういう努力をすべきか、は別の機会に書きたいと思いますが、いずれにしても、「組織において、価値ある存在」となるのは、個人技だけでなく、チームプレイで価値を出す以上は、必ずしも”バンバン売れる営業”、”天才的なプログラマー”、”発想力に優れたプランナー”などということだけではないのです。
関連記事:ギックスの本棚/「ワンピース」と「攻殻機動隊」の組織に関する考察 :「”スキルフルな個人”の集合体」を組織として成立させるためには?